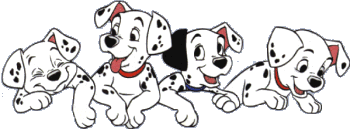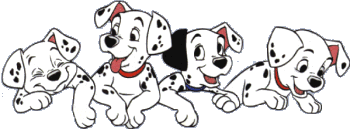|
わかる契約書作り!
●はじめに
契約は、双方の合意あれば、それだけで有効に成立します。これは契約自由の原則においては近代市民法の主要な基本原則ですが、この原則には契約締結方式の自由、つまり、契約を結ぶ形式は各人の自由であり、ともかく契約当事者の意思の合致が認められれば、その方式はどのようなものでも良いという原則が、当然その中に含まれています。
したがって、契約書を作らなければ契約は無効だとか、契約書に調印を済ませていない以上、まだ契約は有効に成立していないというように考える事は、大変な間違いといわなければなりません。
● 文書を作らねばならいない場合
契約を結ぶを方式はあくまで各人の自由で、口頭の契約でも書面による契約でも契約としての法律上の効力には何の違いもありません。しかし、例外として、次の場合には法律が契約書を作るように特別の規定を置き、強く契約の書面かを要請しています。
1. 農地の賃貸借契約…いわゆる小作契約はこれを文書にしてその写しを農業委員会に提出しなければなりません。
2. 建築工事請負契約を結ぶときには、契約書を作成し、工事内容、請負代金、着工期などの事項を記載しなければなりません。
3. 割賦販売法に定める指定商品について月賦販売契約を結ぶときは、売り主から買い主に対して、割賦販売価格や、商品の引渡時期などを記載した書面を交付しなければなりません。
4. 借地借家法では、次のタイプの契約については、契約書の作成を要求しています。
① 存続期間を50年以上とする定期借地権設定契約
② 事業用定期借地権設定契約
③ 更新のない定期建物賃貸借契約
④ 取壊予定の建物の賃貸借契約
⑤ その他
● 契約書を作る上での諸注意
1. 契約の成立時期・有効期間を明記する事
2. 契約の当事者を確定する事
3. 契約の趣旨、目的を明らかにする事
4. 契約の対象・目的物を正確に表示する事
5. 双方の権利・義務のないようをハッキリさせる事
● どこまで契約書に書いたら良いか
簡単に言いますと、法律の規定と同じ趣旨の契約条項は、これを法律に譲って、契約書面の上から省略してもかまいません。これに反して、約束の事項が法律に規定のない場合はもちろん、特に大切なのは、法律の規定と違った取り決めをしようとしたらその点だけはぜひとも契約書に記載しておかなければなりません。
● 契約書は公正証書で
契約書はどんなに、立派に、完全に出来ていても、そればあくまで契約書です。相手が契約に違反をしたとき、その契約書を執行官に持参しても、執行官はその契約書で相手の財産を差押さえたり、競売したりする事は現在の法律上では出来ません。まず、その契約書を証拠として訴訟を起こし、勝訴の判決を受けた上でなければ、相手に対して強制執行は出来ない事になっています。
つまり、契約書というものは訴訟において勝つ為の証拠の切り札でしかないわけです。ここに一般私人が作成した契約書の大きな限界があるわけです。
しかし、同じ契約書でも、これを公証人が作成し、公正証書という事にすれば、今度は性格が変わってきます。相手が契約に違反をしたとき、もはや訴訟を提起して判決を得る必要はありません。
その公正証書じたいが判決とおなじ力を発揮し、それで相手の財産を直ちに差押さえ、これを競売し、その売得金から債権を回収できる一大威力を示す事になっています。つまり、訴訟に要する時間も費用も必要なく、いきなりその公正証書で電撃的に強制執行が出来るわけです。
● どんな場合に公正証書にすると有利か
① 金銭の取立てを目的とした契約
② 手形・株券などの交付を目的とした契約
● 交渉の時に言ってはならない事
交渉中は、交渉中の用語でいくべきです。「承諾しました」というような事は言葉の端にでもいってはならない事のうちに入ります。交渉の途中なのに、契約が成立した、と交渉の相手方に誤解を与えるような発言は厳しく慎まねばなりません。以下は交渉中に慎んだ方が良い用語です。
1. 確定的な事を言う
2. 最終回答という表現を使う
3. 見下す言葉を使う
4. 目的物の悪口を言う
● 交渉を打ち切りたいとき
1. 含みを残す打ち切ります。これは交渉は打切るが、もし自分の方で資金調達が出来たら、第一番に貴殿に声を掛けるから、というような趣旨の事で丁寧に断るべきです。
2. 交渉を打切るコツは、こちらでは契約を締結する意思がなくなったのだという事を、相手にはっきり認識させ、納得させるのが目的ですが、その為にあまり技巧を弄さないことです。率直・正直が大切です。
● 契約が成立したと見られる事柄
1. 履行の着手をすれば契約は成立
2. 金銭の授受があったとき
3. 返事を怠ったとき
4. 注文書又は請書の発送
ただし注文書を発行するだけでは原則的には契約が成立したとはみなされません。
● 訪問販売やマルチ商法ではいつでも契約解除できるか。
8日以内に解除又は撤回
訪問販売では、日常生活ではあまり必要のないもので、比較的高額の商品を売りつけてきます。そこで欲しくもない商品について売買契約が結ばれて、不当に消費者の利益が害されないよう、書面によって、契約の申込みの撤回、もしくは解除通告が出来る事になっています。(訪問販売等に関する法律6条1項)。そして、購入者側に対して、販売業者側から損害賠償などの請求が出来ないように配慮しています。
ところが、無制限に、いつでも、あるいはどんな状態になっても、契約の解除が出来る、という事になると、かえって契約が不安定になり、当事者の公平を失ってしまうのである程度の制限を設けています。その期間は、8日以内という制約があります。ただ、この期間を起算する日がいつかが、ケースによって異なるだけです。
① 契約内容を明らかにした契約書などの書面を受け取った時から8日以内
② 簡単な申込書は書いたけれども契約内容についての詳細な書面は後日持参または送ると言われた時は、実際にその書面を受け取った時から8日以内
③ 一定商品で、一度使用すれば著しく価格が減少するものであって、しかも使用した場合には申込の撤回や、契約解除は出来ないと告げられた場合には、上の8日の期間前であっても、一部でも使用すれば、その時点で、解除などは不可能となります。
効力発生の時
契約の申込の撤回、もしくは、契約の解除には書面でしなければならない事になっています。しかし、このようなクーリング・オフの為の期間が8日という事で、非常に短期間ですので、その法律上の効力は、書面を発送した時に発生する事になっています。しかがって、なるべく郵便を出した、という事が立証できるよう、内容証明郵便を利用する必要があります。(内容証明郵便の詳細はこちら)
マルチ商法の場合
マルチ商法というのは、商品の販売業者のを子、孫、曾孫、というように増やしていくと、その獲得数によって特別な利益が得られるものです。販売商品のないようは洗剤や、化粧品、健康食品などが多いようです。しかも販売する事よりも、販売業者になるように勧誘し、獲得する方が儲かるという事で、大変な弊害が生じたので、前に述べた訪問販売などに関する法律で規制する事になりました。法律では、マルチ商法を連鎖販売取引と読んでおり、一般の人がその餌食にならないよう、訪問販売の場合と同様、クーリング・オフの制度を設けています。
20日以内に解除
マルチ商法について、店舗を利用せずに販売をするという事を契約した個人は、契約締結後、20日以内に、契約解除の通告を書面で発送して行なう事に、一方的に契約を解除する事が出来ます。
ずるい業者のなかには、マルチ商法の概要や、契約解除についての詳細を記載した書面を、契約解除についての詳細を記載した書面を、契約の相手方に渡す義務があるのに、それを怠るものがいるというおそれもあります。そこで、契約を締結したものを保護する為、契約解除のやり方、解除をする事が出来る事などについての説明が契約の締結より後になった場合は、その説明のあった日から20日以内に解除すれば良い事になっています。
● 契約不履行についての法律知識
どんな場合に不履行と見られるか
① 期限を守らない
② 本旨にしたがった履行をしない
③ 債権者側の責任がない事
④ 現実の提供をしない等です。
● 危険な契約条項と見分け方
・契約形式面からのチェックの必要性
なぜ形式が必要かといいますと、正式が整っていないと、証拠としての価値がなくなるか減少するなどの危険があるからです。
たとえば、署名だけでも契約は有効に成立するのですが、印がない場合には、まだ契約が成立の途中であるなどという抗弁が出ないとも限らないからです。ましてゴム印だけでは、証拠としての価値はゼロに近くなるのです。
当事者の住所の記載がない場合にはどうでしょうか。自然人でも法人でも、住所と姓名で特定するのです。ただの山田、鈴木、佐藤では、大工のくまさん、八百屋の八さん以下です。
・無効、禁止、法律違反を原因とする危険な書式
危険な書式のチェックポイントとしては、形式面、当事者の権利義務を明確にするという内容面からのチェックの他に、法律違反による欠陥、すなわち無効となったり、罰則適用の危険のチェックが必要です。
●おわりに
危険な書式の生れる基は何か
社会通念とは何か。これが危険な書式の発生を防ぐ武器です。そのもとは公平という感覚です。一方の側を不当に利するような契約、相手を陥れるような意図を蔵した契約は許されません。「人を呪わば穴二つ」というように、相手に危険を強いるような落とし穴のある書式は自分にも危険な刃を向ける書式である事も多いのです。したがって、公平の感覚に基づいた契約書式は両当事者にとって危険が少ないのです。よく、無欲の人間は詐欺にかからないといわれます。公平な感覚の持ち主は利益につられないからです。
なお、わからない事がありましたらメールで御相談ください。
|