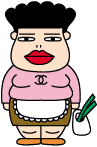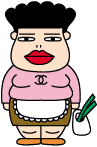|
■ 行列の出来る損害賠償の請求(交通事故の例)
● はじめに
最近、損害賠償をめぐる紛争は増加の傾向にあります。この事は、人々の権利意識の高まりと共に、今日に見られるような高度の技術革新、ライフスタイルや価値観の変容、社会・産業構造の変化等により日常生活の中においても、紛争が起こりやすい状況が生まれている為と思われます。時代が変容するときは必ず新しい紛争が起こるものです。
このサイトではこのような現状を踏まえ、実際に起こりがちな紛争をわかりやすく説明したいと思います。
● 損害賠償を請求する場合にポイントとなるのは、どんな場合に、誰に、いつ、いくら、請求するか、と言う事です。このサイトを読まれた皆様がもっとも気になる所の「自分の場合は果たして請求できるのか。」「費用や時間はどの位かかるのか。」といった問題についても個々の事例が無数にわたってありますのでもし読んでもわからないと言うときはメールで相談をお受けいたしております。
● 事故・紛争・事件・にあった時の心構えと、対策の基礎的、初歩的なものを説明していきます。
1. いつ、どこで(時間と場所の特定)
2. 相手は何処の誰か(当事者の特定)
3. 事実関係の把握は正確に
4. 証拠・関係資料の収集と保全
5. 経過の記録
こう言った事に不安を覚える方は弁護士や行政書士その他地方自治体の市民法律相談を利用してください。
なかでも行政書士は街の身近な法律相談屋さんとして活躍しておりますのでお気軽にご相談してください。
● 話し合い解決の要点
1. 事件の性質が話し合い解決に適しているかどうか
2. 話し合い解決に向いている分野
夫婦・親子・男女その他の家族、親類間のトラブルは離婚や婚約破棄による損害賠償に限らず、土地建物の賃貸借・金銭貸借関係の問題などは話合いでの解決が望ましいと思います。
3. 互譲の精神の気持ちがあるか
4. 人に頼むときは身元確認を
くれぐれも「示談屋」「取立屋」などには頼まないで欲しいものです。逆に訴えられてしまいます。
5. 合意・署名・記名捺印は慎重に
話合い成立の際は、これで一件落着、やり直しは出来ないと決断覚悟してください。示談、和解は紛争に終止符を打つ事が基本ですから、前提に勘違い合ったとか、やっぱり納得しがたいと言う事で蒸し返しは出来ません。
● 損害賠償額の算定
損害賠償の請求が認められる為には、債務不履行にせよ、不法行為にせよ、損害が発生した事、その損害が債務の不履行又は加害行為によって生じた事が必要です。
1. 損害の発生
損害は現実的な損害に限ります。
2. 因果関係
現在不法行為訴訟の分野でっもっとも多くの問題を提供しているのは因果関係論と言えます。
● 損害の種類と損害額の算定
1. 損害の種類
損害を大きく二つに分けると「財産的損害」と「精神的損害」に分ける事が出来ます。
「財産的損害」…所有物の滅失・毀損・利用権の侵害・担保権の侵害・弁護士費用・生命侵害・葬儀費・身体障害
「精神的損害」…慰謝料などです。
● 損害賠償額の具体的算定例
1. 基本公式1
賠償額の範囲=通常損害+特別損害−債権者・被害者が受けた利益−債権者・被害者の過失割合に基づく損害
2. 基本公式2
死者の滅失利益=(基礎収入−本人の生活費)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数または新ホフマン係数
3. 基本公式3
後遺障害による逸失利益=基礎収入×労働能力喪失割合×喪失期間に対応するライプニッツ係数または新ホフマン係数
● 例:被害者:37歳の男子会社員(3児の父)が交通事故で死亡。基礎収入(死亡の際は事故直前の年収)700万円
1. 積極損害(葬儀費用)…110万円………a
2. 消極損害(逸失利益)
・ 本人生活費控除率…年収の35%
・ 稼動可能年数…67歳までの30年間
・ 中間利息控除…年ごとライプニッツ方式
700万円×(1−0.35)×15.3724(37歳のライプニッツ係数)=6994万4420円…・b
<事故がなかった場合に得たであろう退職金>
・ 事故時支給退職金…270万円
・ 定年時(55歳)まで勤務した場合に得たであろう退職一時金…2000万円
・ 中間利息控除後の現価
2000万円×0.41552(55歳−37歳のライプニッツ18年の係数)=831万400円
・ 差引逸失退職金
831万400円−270万円=561万400円……c
3. 慰謝料…………計2300万円
* 損害賠償額=a+b+c+d=9965万4820円(被害者に過失があれば、過失相殺されます。又自賠責保険を受け取っていれば、その額は控除されます。)
● 損害賠償請求と時効
権利が消滅する期間は、権利の種類、発生原因によって分かれています。損害賠償請求権という債権も①債務不履行による場合は、普通は民事債権一般の原則で10年ですが、売買における瑕疵担保責任追及の損害賠償請求は、事実を知ってから1年②不法行為による場合は、損害及び加害者を知ったときから3年、不法行為のときから20年という違いがあります。
①の1年、②の20年というのは「除斥期間」といって法律が予定する権利の存続期間で、時効の中断が認められないという点で、消滅時効と性質を異にしますが、期間内に権利行使をしないと消滅してしまうという点では同じです。
債権・請求権などの消滅時効の時期・除斥期間
・ 一般民事債権(債務不履行による損害賠償請求権)…10年
・ 一般商事債権…5年
・ 不法行為による損害賠償請求権…損害及び加害者を知ったときから3年、不法行為のときより20年(除斥期間)
・ 瑕疵担保責任による損害賠償請求権…瑕疵を知ったときから1年。新築住宅は引き渡しから10年(除斥期間)
・ 判決、和解調書、調停調書、支払催促、仲裁判断などで確定した権利…10年
なお他の損害賠償の事例やもっと詳細な相談は別個メール相談をお受けしております。
|