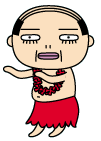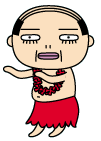|
■遺言のメリット
1.遺言がないと法律どうり!
遺言がないときは法律に決められた配分に従います。
この法律で決められた割合による相続を法定相続といいます。
法定相続は遺言がない場合に用いられる方法であって、遺言があれば遺言に従った遺産相続が行われます。
2.法定相続人以外の人にも遺贈が出来ます。
例えば親身になってお世話してくれた他人やお手伝いさんにも財産を分けてあげられます。
3.相続のトラブルを防げます。
遺言では具体的な遺産の配分方法を指定できます。法定相続は遺産の配分割合に付いて規定していますが、誰が何を受け継ぐかを規定していません。例えば、それまで長い間住み慣れた住居を長男でなく妻に残してやりたい、預貯金や動産をあの人にあげたいなど細かに指定できますから遺産相続のトラブルを防ぐことが出来ます。
4.一度書いた遺言でも取消し・書き直しは自由
せっかく遺言を書いても後になって後になってああすればよかった、こうすれば良かったと思い返すこともあります。年月が経つと財産の価値の変動もあるでしょうし、また相続人の状況に変化が生じてくるかもしれません。でも心配いりません。遺言は一度書いても取り消しや変更ができるのです。ですから、書いてさえ置けば後で気持ちが変わっても書き直しをすれば良いわけなのです。
■遺言で出来ること
遺言によって出来ること出来ないことがあります。つまり、法的な拘束力をもつものともたないものがあるのです。そこをはっきりしておかないと、せっかく遺言を書いても無駄になってしまいますから、そのポイントをしっかりと押さえていく必要があります。
まず遺言で出来ること
1.
身分に関すること
隠し子の認知
未成年者の後見人などの指定
2.
相続に関すること
相続分の指定が出来る
遺産分割方法を指定できる
遺産の分割を一定期間禁止できる
相続人相互の担保責任の変更が出来る
特別受益分控除の免除が出来る
相続人の排除とか、その取消しが出来る
祭具などの継承者を指定できる
遺言執行者の指定が出来る
財産処分に関する事
遺贈が出来る
寄付行為が出来る
信託の設定が出来る
■遺言で出来ないこと
1.
結婚や離婚に関すること
2. 養子縁組に関すること
3. 遺体解剖や内臓移植に関すること
■ さまざまな遺言方式
遺言は偽造や変造があったり、誤解や意味不明があってはならないため、民法に定められた方式に従わなくてはなりません。これに従わないと法律上、遺言としての効力は認められません。せっかく書いた遺言が書式上の欠陥のために無効になるようでは、何のために書いたのかわからなくなってしまいます。遺言書には通常の方式として3つあり、その他に緊急な場合などの方式があります。緊急の場合はさて置き通常の遺言書にはそれぞれ長所と短所がありますから、自分に一番ふさわしい書式を選択するようになさってください。
遺言の種類
1. 自筆証書遺言
自筆証書遺言は自分で書く遺言です。紙と筆記用具があり、文字さえ書ければできます。また書いた内容を自分だけの秘密にしておけますし、公証人・証人・立会人・などを頼む手間も要りませんから、素も意味では非常に簡単に作成できますしまた、費用もかかりません。ただしそのような長所もあるものの、書式上の決まりがありますから、それを間違うおそれもあります。したがって、書く以前に民法に規定されている方式の重要ポイントをきちんと把握しておきミスを未然に防ぐ配慮が求められます。
ではそのポイントを紹介します。
● 内容はすべて自分の手で書く
● 年月・日付を必ず記載する
● 氏名を自分で署名して押印する(実印が好ましいが認印でも拇印でも良いとされています。)
● 加除訂正にも方式があります…遺言書に文字を加筆したり訂正したりする場合、その場所を指示して、変更した事を欄外に付記して、その部分に署名しなければなりません。また、加除した場所に署名の下に押したものと同じ印鑑を押します。
● 平易で誤解のない言葉を使用する
● 封筒に入れて封印する方がよい
2. 公正証書遺言
公証人が作成する遺言書が公正証書遺言です。公正証書遺言書は公証人が遺言者の口から聞いた内容を、公証人が法律の規定どうりに作成したものです。この方式だと自筆証書遺言のように方式の不備による遺言の無効という危険は少なくなります。公証人の手数料は公証人手数料で決められていますが、財産価格に応じて手数料は変わります。一応の目安としては五千万の財産価格で二万五千円程度で、それを越す時は五千万ごとに一万二千円加算されます。
公正証書遺言作成の準備事項
●証人二人以上(友人・医師・看護婦・弁護士・行政書士等。 なお未成年者・禁治産者・準禁治産者・推定相続人・受遺者とその配偶者・直系血族・公証人の配偶者・四親等内の親族・書記・雇人は証人としての資格はありません。)
● 遺言者の実印・印鑑証明書一通(六ヶ月以内のもの)
● 遺言するべき内容を整理しておきます。
● 戸籍謄本・抄本・住民票
● 不動産登記簿の謄本又は抄本
● 固定資産税評価証明書
3. 秘密証書遺言
これは遺言の内容を秘密にして保管するための方式です。この方式ですと、遺言をかならずしも自分で書く必要がありません。他人に代筆をイライしてもかまいませんし、ワープロ等で記載しても良いのです。また印刷でもかまいません。封をされた遺言書に遺言が収められていることを、公証人一人と証人二名が立会って公正証書の手続きで公証しておきます。しかし、この遺言書は公証人の手元に残されませんから、破棄や隠匿の可能性がないわけではありません。保管には十分気をつける必要があります。また、遺言の内容について公証人や証人は知らされていませんから、遺言としての不備や記載内容の不明確などで紛争が起こりやすい欠点あります。開封は自筆証書のときと同様、家庭裁判所で行われなければなりません。家庭裁判所以外で勝手に開封した場合には過料が課せられます。
秘密証書遺言者の作成手順
● 遺言者に遺言者の署名と押印が必要(署名は自筆に限ります。)
● 日付は必ずしも必要ではない
● 加筆・訂正は自筆による
● 遺言書と同じ印鑑で封印
● 公証人に遺言書を提出
● 公証人などが封印に署名押印
● 証人の資格は公正証書遺言書の場合と同じです
|